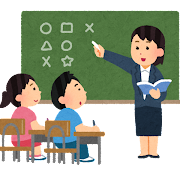春――。新しいランドセルを背負って歩く子どもの姿に、胸がじんわり温かくなる季節ですね。
「うちの子も、いよいよ小学生か!」
そんな嬉しい気持ちの一方で、ふと気になるのが――
「義務教育だから学費はタダ」と思っていた方も多いかもしれません。
でも、実際はそう簡単ではないんです。
この記事では、**農薬・肥料業界歴25年以上の現役サラリーマンパパ(筆者)**が、文部科学省の最新データと自分の実体験をもとに、リアルな教育費を公開します!
Contents
📘この記事でわかること
-
小学1~3年生に実際にかかった年間学習費(リアルな数字を公開)
-
「教育費」と「養育費」の違いをわかりやすく解説
-
子育て世帯がもらえる支援金・助成金の活用法
【信頼性バツグン】データ出典は文部科学省!
「個人ブログの体験談だけでしょ?」と思われる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
この記事は**文部科学省の『令和5年度 子供の学習費調査』**をもとに作成しています。
公立小学校の年間学習費(授業料・給食費・習い事などの合計)は――
👉 年間336,265円(1人あたり)
内訳は以下の通りです。
| 区分 | 内容例 |
|---|---|
| 学校教育費 | ランドセル、文房具、体操着、教材費など |
| 学校給食費 | 給食費全般 |
| 学校外活動費 | 塾・通信教育・スポーツ・英語教室など |
💡実例公開:現役パパのリアル学習費!
「うちの場合、実際どうだったの?」
そんな疑問にお答えして、我が家の実データを公開します!
| 学年 | 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 小1 | 136,828円 | 44,482円 | 248,479円 | 429,789円 |
| 小2 | 46,492円 | 44,962円 | 271,473円 | 362,927円 |
| 小3 | 49,451円 | 3,790円 | 287,482円 | 340,723円 |
平均より高いのは、「入学準備」と「習い事費用」が原因。
特に小1ではランドセルや教材を張り切って揃えた分、出費がかさみました。
🎯教育費と養育費の違いを整理!
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 教育費 | 塾・教材費・授業関連費など、学びに直接関わる費用 |
| 養育費 | 食費・衣服・医療費・生活用品・おもちゃなど |
我が家では、お下がりの服や家具をフル活用!
いとこから譲ってもらった学習机やランドセルは本当に助かりました。
一方で、七五三や習い事など、「どちらの費用?」と迷う支出もありますよね。
💰子育て世帯がもらえる「お金」も賢く活用!
●児童手当(国の支援)
子ども1人につき月額1万円〜1万5千円(所得により異なる)が支給されます。
筆者も年間6万円ほどを受給。学用品費の足しになりますね。
●子どもの医療費助成(自治体支援)
自治体によっては、小学生まで医療費が無料または上限付きのところも!
我が家の地域では小2から再び助成が復活し、大助かりでした。
👉 自治体HPで「医療費助成」「子ども手当」を検索してチェックしてみましょう。
🧮我が家の教育費まとめ(小1〜小3)
| 項目 | 累計費用 | 年平均 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 232,771円 | 約77,590円 |
| 学校給食費 | 93,234円 | 約31,078円 |
| 学校外活動費 | 807,434円 | 約269,144円 |
特に「学校外活動費(習い事)」が突出。
妻と一緒に「習い事の月額予算会議」を開く予定です(笑)
✨あとがき:子育て費用は「見える化」で不安を安心に変える
子どもの成長とともに増える教育費。
でも、こうして数字で「見える化」すると、どこに力を入れるべきか、どこを節約すべきかが見えてきます。
教育費は「将来への投資」。
焦らず、無理せず、家族で話し合いながらバランスをとることが大切だと実感しています。
👨👩👧筆者プロフィール
-
名前:運雄新記(unyushinki)
-
職業:会社員(26年目)
-
家族構成:妻と小学生の娘
-
座右の銘:「素直な心はあなたを強く、正しく、聡明にいたします」
-
ブログ理念:「三方良し(読者・広告主・自分)」
💬まとめ
✅ 小学校入学には意外とお金がかかる
✅ 習い事は「月額予算」を決めておくと安心
✅ 支援制度を調べて、もらえるお金はしっかり活用
この記事が、これから小学校入学を控えるパパ・ママの参考になれば嬉しいです。
あなたの家庭の「教育費バランス」を考えるきっかけにしてみてくださいね。
🪄おすすめ関連記事
👉 【実録】戸建てオール電化の電気代、住み替え前と比較してみた!賢い節約術も公開
👉 【図解】新NISAの仕組みと始め方|2025年版・初心者向けにやさしく解説